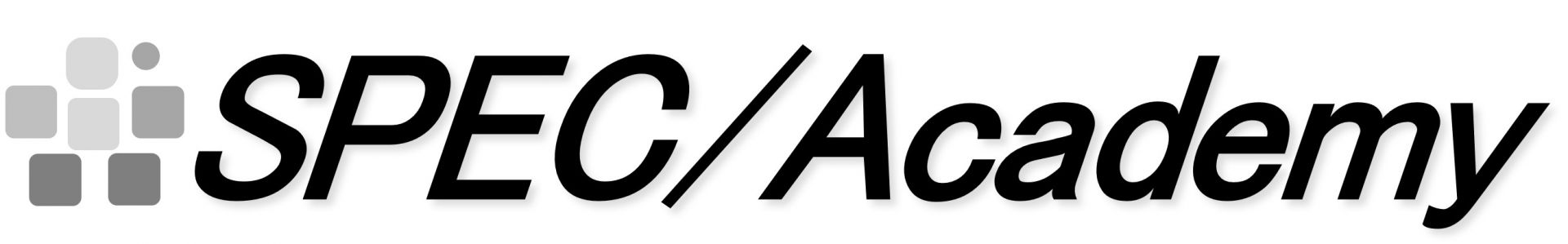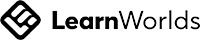本書は、2011年9月29日にさいたま市立小学校で発生した桐田明日香さん(当時小学6年生)の死亡事故を契機として生まれた、学校における救急対応モデル「ASUKAモデル」の誕生経緯、内容、そしてその後の影響を包括的に記録したものである。明日香さんはマラソン練習中に心停止で倒れたが、現場にAED(自動体外式除細動器)があったにもかかわらず、適切な救命処置が行われずに命を落とした。
この悲劇は、学校現場における危機管理体制の脆弱性を浮き彫りにした。特に、心停止の兆候である「死戦期呼吸」の誤認、教職員の知識・スキル不足、そして緊急時の組織的対応の欠如といった深刻な課題が明らかになった。当初は学校側と遺族との間に対立と不信があったが、明日香さんの母親である桐田寿子氏の「二度とこのような事故を起こしてはならない」という強い願いが、さいたま市教育委員会を動かし、両者の協働による再発防止策の策定へとつながった。
その成果が「ASUKAモデル」である。このモデルは、誰もが突然の事態に直面した際に、簡潔かつ的確に行動できるよう設計された実践的な危機管理マニュアルである。その中核は、「反応なし・普段通りの呼吸なし」を確認した場合、直ちに「119番通報、AED手配、胸骨圧迫」を開始するというシンプルな行動指針にある。
さいたま市では「ASUKAモデル」の導入と全教職員を対象とした年1回の救命講習が義務化された。その結果、教職員が救命活動を行うことへの自信は飛躍的に向上し、学校の安全文化は大きく変容した。本書は、一人の少女の死という悲劇を、多くのいのちを救うための具体的な教訓とシステムへと昇華させた記録であり、全国の学校安全と救命教育のあり方を考える上で極めて重要な示唆を与えている。
ある時、私はさいたま市教育委員会委員長の桐淵氏から電話をもらいました。それは「事故調査をやり直したいので分析手法を教えてください」という趣旨の内容でした。
そこで、私が当時の教育員会のメンバーに分析手法の講義をして、実際の分析にはImSFER研究会のメンバーが中心となって再分析を行いました。
事故の分析には、医療現場で用いられるヒューマンファクター工学に基づいた分析手法(Im-SAFER)が用いられました。
これにより、個人の責任追及ではなく、システム全体の問題点として課題を抽出することができました。
分析の結果、以下の7つの主要な教訓が明らかになりました。
1.
痙攣や死戦期呼吸は心停止のサインであると知らなかったこと
教職員は、倒れた直後の痙攣やあえぐような呼吸を「呼吸あり」と誤認した。これは心停止の典型的な兆候であり、この知識の欠如が初動の遅れを招いた最大の原因であった。
2. 熟達した医療従事者以外は脈をとるべきではないことを知らなかったこと
一般市民が緊急時に正確に脈を触知することは極めて困難である。ガイドラインでは脈の確認を推奨しておらず、「反応なし・普段通りの呼吸なし」を心停止の判断基準としているが、この点が現場で理解されていなかった。
3. AEDは診断機能があり、誤って電気ショックを与える危険はないと理解が不十分だったこと
AEDが自動的に心電図を解析し、必要な場合にのみ作動するという安全性への理解が不足していた。「ただちに使おう」という認識が欠けていた。
4. 「子どもが倒れた!」という想定訓練をしていなかったこと
学校の危機管理マニュアルは存在するものの、火災や地震を想定した訓練が主であり、児童生徒の突然の心停止を想定した実践的な訓練は実施されていなかった。
5. 養護教諭に頼りすぎていたこと
多くの教職員が、救命処置は養護教諭の専門業務であると過度に依存していた。しかし、養護教諭が不在の場合や、現場から離れている場合に対応できず、組織としての対応能力を著しく低下させていた。
6. 教職員の危機意識の問題
「元気な子が突然死に至ることはない」という思い込みがあった。学校管理下での突然死のリスクを正しく認識できておらず、危機意識が希薄であった。
7. 「正常性バイアス」が生じたこと
予期せぬ異常事態に直面した際、「大したことはないはずだ」と思い込もうとする心理的な罠(正常性バイアス)が働き、事態の深刻さを過小評価し、行動をためらわせる一因となった。