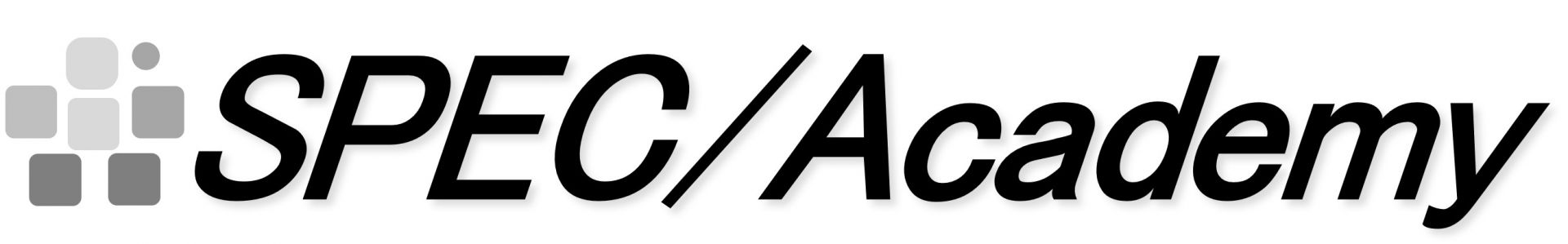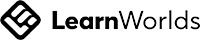東京女子医科大学は、過去に二つの重大な医療事故を起こし、社会から厳しい評価を受けました。東京女子医大は、この事実を正面から受け止め、反省を言葉だけで終わらせない仕組みをつくる必要があると認識しました。日本航空の
「安全啓発センター」がそうであるように、事故の経緯や背景を“見える化”し、教訓を世代を超えて伝え続ける場を大学の中に常設する――それが、東京女子医大の再出発の第一歩だと考え、今回の取り組みとなりました。
私は航空や原子力の世界で安全の問題、特にヒューマンエラー対策に取り組んできました。航空や原子力の世界では、設計・運用・教育・監査が分厚く制度化され、体系だった安全要件が積み上げられています。
一方、医療は初診情報の不完全性や変動の大きい現場環境、未解明な医学的要素、患者の生活要因など、構造的にリスクを抱えています。ゆえに同じ“安全”を語っても、医療は前提条件が違うのです。ここを共有しなければ、現場の努力は空回りし、社会の期待ともすれ違うと考えらえれます。。
女子医大の立場は明快です。安全はゴールではなく、常に管理・調整すべき“関係”であり過程です。実務の世界では「安全そのもの」は実体ではなく、「許容できないリスクがない状態」を指します。つまり、起こりうるリスクを洗い出し、許容水準に抑える営みを続ける以外に道はありません。
私が鼎談で主張したことは、この認識に立てば、ヒューマンエラーは原因ではなく、結果として現れる現象であること理解すべきであることです。忙しさ、情報の見づらさ、手順の未整備、名称や容器の類似、経験や体調――こうした人間側と環境側の要因が噛み合わない時に、エラーは誘発されます。だから対策は「注意せよ」ではなく、設計・表示・手順・情報・チームワークを変えることに向かうべきなのです。これをみんなで実現しなければならないのです。
東京女子医大は、医療安全啓発センターを「学内の記憶装置」にし、過去の事故・ヒヤリハットの事実と背景、判断を支えた情報の流れ、環境や組織の条件、そこから得た教訓――これらを常設展示と体験教材(動画・VR・シミュレーション)として可視化する予定です。当然のことですが、目的は、犯人捜しではなく再発防止のためにみんながそれぞれの立場で学習ことです。医療者だけでなく、一般の人・学生・患者さんが来館し、“安全とは何か”を対話する共通の場となるといいと考えています。
これは私の期待ですが、私たちは、過去の事故から目をそらさず、「安全はない。あるのはリスクだけ」という現実を出発点にしてもらいたいと思います。そして、エラーを生む構造を科学的に変えること、患者・一般の人と協働する文化を育てることを大学として取り組んでいただきたい。事故の記憶を展示し、対話と学びの場に変える――医療安全啓発センターは、その意思のかたちです。二度と同じ事故を繰り返さないために、風化させないための場となって欲しいと思います。
世の中に安全はない。リスクのみ存在する
医療システムは構造的に問題が大きい